ホーム > 雑文・文献・資料 > 縁起
縁起
釈尊が覚った縁起は「法」という名称でも呼ばれ、次のように示されている。
「法」そのものは東西古今を貫く真理であって、いわゆる
「如来世に出ずるも出でざるも、この法は常住である」
(パーリ相応部一二・二〇、雑阿含経巻第十二)
といわれるところのものである。仏陀はただこの法を証っただけであって、仏陀の教えを 聞いてこの法を証る人は、 何人といえども仏陀と同じさとりの境地にまで到り得る、とせられている。 すなわち、歴史的事実としては、 ゴータマ仏陀がこの法を証った最初の人であるには違いないが、 それは、仏陀が初めてこれを作り出した、 ということを意味するものでもなければ、また他の人が これを作り出した、ということをいうものでもない。 仏陀はただ発見者に過ぎない、とせられている。 それ故にまた、仏陀みずから
「私は古仙の道を進んで、古城を発見したようなものである」
(パーリ相応部一二・六五、雑阿含経巻第十二)
ともいっておられる。
[仏教学序説64]
すなわち縁起は「東西古今を貫く真理」であり「仏陀はただ発見者に過ぎない」のである。 この部分の物言いだけを見ると、まるで万有引力の法則を発見したニュートンの逸話に繋がるような イメージがある。それは近代的思考への近しさであり、我々現代人が違和感無く受け止めることの 出来る世界観である。そのイメージの近しさが「仏教は合理的」 であるといった見方にも繋がっている。 その時、ここで言う「法」とは自然科学の「客観的法則」に類似のものとして捉えられてしまう。 これによって多くの人が仏教にある面で好意的な感想を持つと共に、その感想によってまた仏教の根本 を見る目を失ってしまうのである。何故このような捻ひねった言い方をするか。 それは「法」たる縁起は、また次のようにも示されるからである。
仏伝によれば、釈尊は縁起の観察によって正覚を成就して覚者となったが、・・・自分が覚証の内容 たる縁起の道理は甚深じんじん難解なんげであって、執着を楽しみ、執着を悦び、 執着を喜ぶ人々にとっては、その 甚深難解なる縁起の道理を説いても、到底解了げりょうし 難いであろうと。その思いが次の如く偈げで綴られている。
わが成道は極めて難し。巣窟にあるもののために説くも、貪恚とんに愚痴の者は、この法に 入ることあたわず。 逆流して生死に回る。深妙にして甚だ解し難し。貪恚愚痴の者は欲に著して所見なく、 愚痴によって身み覆おおわるればなり。
そういう事情で、それを説いても了解せられず、徒らに自ら徒労疲苦するのみであるから、それを断念して、 むしろ三昧に入って所証を楽しむにしかず、ということになり、沈黙して法を説かずということになった。 その時に、娑婆しゃば界の主、梵天が、遙かに仏陀の心の中を知って、そういうことでは、 この世間の大敗壊はいえとなるであろうと考え、梵天の世界から姿を隠して仏前に顕われて、 「世間には、垢の薄少で智慧聰明な者もいるから、どうか説法をせられるように」と勧請かんじょうした。 仏陀は、さきに静閑処で思惟したところを述べて、説法しない意図を述べられたが、重ねて、梵天は仏陀に勧請した。 そこで仏陀は種々と思惟せられた上で、バ ーラナシーの鹿野苑ろくやおんにいた五比丘の処へ往き、 そこで初めての説法が開陳せられ、 五比丘が済度せられた。
[仏教学序説107]
「法」たる縁起は「甚深難解」であり、他者に説明しても「了解せられず、徒らに自ら徒労疲苦するのみ」である
と釈尊は判断し「沈黙して法を説かず」と決断したというのである。これは尋常ではない。何故なら「法」が
「客観的法則」のようなものであれば、それは言葉で論理的に説明出来るはずである。そしてその内容が如何に
複雑高度であろうと、意志のある者には理解できるものでなければならない。ところが釈尊は「沈黙して法を説かず」
と決めたのである。これは覚った釈尊の傲慢なのか。しかし伝記にて釈尊の性格、覚りに至るまでの過程、成道後の
後半生の振舞等を読むとそのような慢心があったとはとても思えない。そうだとすると、どうも「法」は我々が考える
ような「客観的な法則」とはそもそも異質なもののようである。
そうして沈黙を決断した釈尊の心中には新たな問題が屹立する。その問題を仏伝は梵天の勧請という、当時の
インドの世界観に根ざした神話的流儀で語る。この場合の梵天とは世界の支配神とみなしてよい。その世界の支配者
たる神が釈尊に、沈黙を破って覚られた「法」を世間の人々に語って欲しい、と頼んだのである。 この神話を
現代語で捉えなおせば、全人類のために覚った法を説くべきではないか、という釈尊の心中に起こった要件を
表していると言える。説法の対象が「全人類」である。何故そう言えるかというと勧請したのが全人類の生息する
世界の支配者たる「梵天」だからである。一人や二人、十人や百人が対象であればわざわざ梵天を出す必要はなく、
もっと卑小な神でいい。
そして、この話は覚りを得た釈尊に避けがたく立ち現れた課題であったことを表現している。 覚りがコインの
表側の顔であったとすれば、説法の要請は裏側の顔であった。説法を避けて通ることは出来ない。しかし覚りは
「甚深難解」で言葉で解説できるものではない。しかも説法の対象は全人類である。これらの、矛盾とも言うべき
困難とスケールの大きさに直面し、釈尊は「種々と思惟せられた」のであろう。そして遂に釈尊は思惟から立ち上がり、
説法を開始したのである。
縁起の型「此れ有るとき、彼れ有り」の
表現は論理的である。そして「論理的」ということは、現代の我々にとっては「合理的」とほぼ同義である。
「合理的」とは「これ」と「かれ」に対象を
あてはめ、 言葉によって全てが明白に表現できるもの、という考え方である。
縁起の型の句を我々が見た場合、そのような「合理性」を表現している句であろうという先入観を、
ほとんど無意識的に持ってしまう。そして縁起の内容とは、その類の合理性を表したものだ、と思い込む。
ここで先ず縁起を正しく理解する道を誤る。
さらに縁起の説明で種子と芽と土と栄養と水と光などに例えて因縁果が表されると、我々にとっては
まるで理科の初歩である。そこで、縁起は「科学的な客観的法則」を述べたものという、早合点の思い
込みを懐くようになる。ここで再び縁起の正しい理解への道を誤る。
これが縁起の句を目にした時に我々現代人が最初に受ける「表」の印象である。
それでは「表」の誤った印象の「裏」に隠れている内容は何か。
我々が通常「此れ有るとき、彼れ有り」という意味の論理表現を使う目的は、ある結果に対して原因を
確定したい、あるいはある原因に対して結果を確定したいためである。そうすることにより問題を
理解し安心したいと欲求する。
しかし縁起でこの表現が使われる場合は「此れ」とは何ものかを不確定的に示す意味を持つ
([仏教学序説83])。そして縁起を語る文脈では必ずそのように使われる。
(限定している場合でも、その限定は任意の限定の組の一つでしかなく、他の任意の限定の組に置き換
え可能である。)よって原因あるいは結果を確定しようという意図、すなわち対象を絞り込んでいって
特定しようという意図をはぐらかす働きを内在することになる。
例えばこの縁起の型が十二縁起
として表現された場合は、 いかにも原因を特定するような表現の連鎖になるのだが、その一方で
連鎖が十一も続くことによる居心地の悪さを読むものに与えずにはおかない。その居心地の悪さは、
このはぐらかしの働きが顕在化するための故である。
これは別の言い方をすれば、「〜によって〜あり」という論理性の表現が、その使い方において論理の
無限の連鎖に繋がる方向付けをされているため、原因を特定するという意味での論理性を破壊する効果を
上げているということである。
なぜ論理によって論理を破壊するという矛盾した破天荒な仕組みを作り上げているのか。 それは、
その仕組みによって論理ではとらえきれない次元を暗示し、それこそが重要であることを示すためである。
これが縁起の型の表現の「裏」の内容であり、真の相すがたである。
この縁起の型は本来「これを縁とすること
(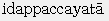 イダパッチャヤター )
」と言われ([仏教学序説83])
此縁性しえんしょうと漢訳される。すなわち此縁性という性質は、論理表現において自身
の論理性を破壊し、論理によっては表現されないものを暗示する、というものである。
イダパッチャヤター )
」と言われ([仏教学序説83])
此縁性しえんしょうと漢訳される。すなわち此縁性という性質は、論理表現において自身
の論理性を破壊し、論理によっては表現されないものを暗示する、というものである。
「言葉になった」縁起の教説にはこのような背景がある。そこには言葉に出来ぬものを言葉にしようとする 苦心と技巧と緻密な組み立てが幾重にも格納されている。その多義性が縁起を知ろうとする我々には、 様々な難関となって現れてくる。