ホーム > 雑文・文献・資料 > 葬式の段取り
葬式の段取り
2014年6月21日 同朋の会
葬式の段取りとその意味について解説するということで案内しましたが、「意味」をどこまでお話できるか、実は全く自信がありません。
皆さんは人の葬式に出たり、自分の家の葬式を出したりされています。他人の葬式に出るのはそこまで言うと語弊があるかもしれませんが、義理で出るということですね。ただし、それを欠かしたらまともな人と見なされないくらいの重要な義理ですね。皆さん当然の如く他人の葬式に出るし自分の家の葬式を出しますが、葬式は過ぎてしまえば終りだと思いませんか。葬式の場にいるときは大変ですが、とにかくその場をこなす。弔問に行ったり通夜に行ったり儀式に参加したり。しかし、それがどういう意味なのか普通は考えもしないと思います。宗派によってやり方がずいぶん違うんだな、くらいは感じるでしょうが。
そういう葬式の流れと内容をきちんと説明できるといいのですが、納得できる説明が出来るものは葬式の中の何割もありません。
というのもきちんとした意味があって儀式の形が決まっているようなことは少なく、多くは「やることになっているからやる」といった程度のことでしかないからです。情けない話ですが、葬式というものはそういうものです。と、最初から白旗を揚げるようなことでは、話にならないので何とかしていこうと思います。そしてまた、少ないながらも意味のある事柄がありますので、そういうものを拾いながら説明していこうと思います。
葬式の進行のパターンは地方によって違いますので、まず最初に、仙台で一般的に行われる葬式の手順を書いてみます。
1.遺体の安置
普通は自宅に安置となりますが、今の世の中それが難しい場合があります、そのときは葬儀屋さんの会館や寺に安置ということもありえます。この時点で当然葬儀屋さんが介在していますから、そのビジネスの中で動くという面もあります。
2.枕経
坊主が遺体の安置場所に行って簡単なお勤めをしてから葬式全体の打合せをします。この時のポイントが火葬場の予約ですね。それが決まって全体の式の流れが決まる。仙台の場合、市営の葛岡の火葬場ですが、ここは休みは無いはずです。しかし、友引の日は休みになる火葬場もあります。仙台の場合は友引に火葬にできます。そして火葬の日がだいたい葬式の日になりますので、友引に葬式を出すということもできるわけです。我々坊主も友引に葬式しても問題ないですと言います。しかし友引に葬式を出すということに抵抗を感じる人達は多いので、友引を避けて日程調整する場合がほとんどでしょう。
3.納棺
この時には葬儀屋とは別に納棺師という業者が介在します。昔は納棺は遺族がやっていたのですが、今は業者に任せるのが大半だと思います。
4.申経(もうしぎょう)
通夜までの日にちが空く場合、毎日短いお勤めをしに行きます。これも時代の変化で、昔は行くのが当然でしたが、最近は申経に来ますか、と確認してから行くようにしています。来られても人がいないという場合もありうる時代ですので。
5.通夜
葬式の前日の儀式です。
6.出棺
火葬場への遺体の移動です。
7.火葬
火葬になって遺骨を拾う時に、前々回話題にした「箸渡し」が出てきます。
8.葬式(告別式)
私は「告別式」という言い方が嫌いで、葬式と言っています。全体の流れも葬式と言えるのでややこしいのですが。本葬という言い方もありますが。告別式とは葬儀屋さんが作り出した言葉かなと思っていますが、別れを告げる儀式という意味合いです。しかし葬式は別れを告げるためにやっているわけではありません。そういうことで告別式は使いたくないのです。
9.繰上法要・中陰(ちゅういん)
繰上法要は仙台特有でしょうか、四十九日、百ヶ日の法要までやったことにしてしまう。ほかに東北のどのあたりでやっているか分からないのですが、東京から南では繰上法要はあまりやらないようです。繰上法要をして斎食(食事)をしている間に、葬儀屋さんは自宅に仮の祭壇を設置します。これは四十九日までの期間、すなわち中陰の期間中設置するものなので中陰壇(ちゅういんだん)と言います。
最近は、出棺の前に葬式を行う場合も増えています。この場合は時間と手間が少し省けます。
では次にそれぞれの項目の意味に入っていきます。
1.遺体の安置
 これはお釈迦様が亡くなった時の様子を描いた釈迦涅槃図(しゃかねはんず)と言われるものの一つです。お釈迦様は三十五歳で覚りを開いたといわれます。覚りを開いた人のことを仏と言い、覚った内容を涅槃とも言います。つまりお釈迦様は生きているうちに涅槃を得たのです。
これはお釈迦様が亡くなった時の様子を描いた釈迦涅槃図(しゃかねはんず)と言われるものの一つです。お釈迦様は三十五歳で覚りを開いたといわれます。覚りを開いた人のことを仏と言い、覚った内容を涅槃とも言います。つまりお釈迦様は生きているうちに涅槃を得たのです。
それは煩悩の身体を持っていての覚りでした。しかし、八十歳で亡くなった時には、煩悩の身体が消える。そして三十五歳で得た覚り・涅槃と、煩悩の身体が無くなることにより完全に一致する。お釈迦様が死んだということをこのように表すのです。覚りを得るということはこの上ない喜びです。そして身体が死ぬことによって完全な覚りと一致することも喜びである。死というものをそういうふうにとらえるのです。
ふつう死んだら悲しいということが前面にでてきます。この絵でもそうです。周りの人や生き物は泣いています。しかし本人にとっては涅槃と一体になるという喜びがある。ですから仏教においては死は悲しみと喜びの二重性がある。葬式の中で表白(ひょうびゃく)という文章を読み上げる場面がありますが、その文章では悲しいことをほとんど出さす、喜びであるという表現がでてきたりする。それはここで説明した立場があるからです。
と、ここまでは理屈です。実際の葬式ではお釈迦様のような死に方をした人はまずいません。しかし、葬式という儀式の組立ての中には、お釈迦様の亡くなり方をまねるということが入っている。
その形が頭北面西右脇(ずほくめんざいうきょう)と言って、頭を北に顔を西に向け右腕を枕にして横たわるという姿勢です。だから北枕というのです。北枕で昼寝なんかをしたら、家族から「北枕なんか死んだときだけだ」と怒られる。死者をお釈迦様が亡くなった形に似せて横たえる。ですから本当なら、北枕の上に右脇を下にして寝せなければならない。儀式の教科書には、寺族が亡くなったときはそこまでした方が良いと書いてあります。しかし、西照寺の寺族の場合は右脇を下にすることまではやっていません(一同笑)。そこまでするところはほとんどないと思います。
さて、一般的には北枕は不吉な事として嫌いますが、私はこの前の箸渡しの話と同じで、そういう考えがほとんどありません。時々北枕で昼寝をします。(笑)
ここからは六年前に亡くなった母の葬式を例に出しながら説明します。
 |
 |
これが、庫裡(くり)の仏間で平生は観音さんの軸が掛けてあります。その左側に仏壇があります。
 母が亡くなって遺体を安置したときはこのようになりました。床の間の中身が変わりました。軸が阿弥陀如来の絵像、その前に三具足(花瓶、土香炉、燭台)が並びます。花瓶には櫁(しきみ)を活けます。下の台は葬儀屋さんがもってきてくれたもので、サイズがちょうどよかったので使いました。そして遺体の前に焼香用の机を置きます。本来はこれだけでいいのです。焼香机の両脇の花瓶は本来はいりませんが、葬儀屋さんが持って来たので置いているだけです。
母が亡くなって遺体を安置したときはこのようになりました。床の間の中身が変わりました。軸が阿弥陀如来の絵像、その前に三具足(花瓶、土香炉、燭台)が並びます。花瓶には櫁(しきみ)を活けます。下の台は葬儀屋さんがもってきてくれたもので、サイズがちょうどよかったので使いました。そして遺体の前に焼香用の机を置きます。本来はこれだけでいいのです。焼香机の両脇の花瓶は本来はいりませんが、葬儀屋さんが持って来たので置いているだけです。
このとおり床の間には本尊の軸が掛かります。これは亡くなった時そうするというだけでなく、本来は床の間は本尊を飾る場所なのです。ですから理屈では床の間があれば仏壇はいらないのですが、我家ではそこまで理屈を通してはおらず、世間一般と同じように床の間と仏壇があります。また他宗派の場合は遺体を安置したとき仏壇を閉めるようですが、我が宗派はしません。仏壇は開けたままで、灯明を点け花を供えます。
2.枕経
先に説明した通りです。
3.納棺
身に付けるものは白服(はくふく 白い襦袢)、念珠。これだけです。昔はこの着せ替えは家族や縁者でやったようですが、今は納棺師という業者が代行してくれるようになった。その作業がまた実に見事なわけです。遺体に寄り添ってするすると着せ替えしてくれる。その技術にはびっくりしますし綺麗にお化粧もしてくれます。しかし家族が遺体に手を触れないでそういう処置がなされてしまうということは善し悪しですね。母の時も複雑な気持ちで納棺師の作業を見ていました。次に納棺しますが、その時お棺の蓋の裏側に名号と法名を書いた棺書(かんじょ)というものを本来ならば貼ります。ところが西照寺では棺書は貼りません。なぜかというと、これまでやっていなかったから(笑)。おそらく納棺の時点では法名がまだ決まっていない場合がほとんどなので、貼らなくなったのかとも思います。母は生前に法名は付いていましたが。
これからは、法名を持っている方が亡くなった場合は、棺書は書かなければならないかな、とも思っています。
 母の時は密葬と本葬の二回、葬式を行いました。密葬は本堂は使わず、仏間で行いました。この頃になると供花とか写真とかで賑やかになっています。小さくて見にくいですが、白木の位牌ではなく法名軸が飾ってあります。母の場合は事前に用意していたので飾ることができました。
母の時は密葬と本葬の二回、葬式を行いました。密葬は本堂は使わず、仏間で行いました。この頃になると供花とか写真とかで賑やかになっています。小さくて見にくいですが、白木の位牌ではなく法名軸が飾ってあります。母の場合は事前に用意していたので飾ることができました。
4.申経
先に説明した通りです。この時は毎日定刻にお勤めしていました。
5.通夜
 |
 |
密葬の通夜はこの通り、仏間です。10日くらい後の本葬では、本堂にこのように段を飾りました。
花瓶に挿してある銀色のものは紙花(しか)と言います。金色、銀色、白色の紙で作ります。これはお釈迦様が亡くなった時に、その場に生えていた沙羅双樹という樹まで嘆き悲しんで枯れてしまったという伝説から、枯れた樹を表わすために生花でなく紙で作った花を飾ると言われています。
6.出棺
先に説明した通りです。
7.火葬
先に説明した通りです。
8.葬式(告別式)
 これは母の本葬の時の写真です。寺族の葬式ですので坊さんがいっぱいいます。普通の人の葬式の場合は、
前住職がまだ仕事ができた時は、二人で勤めるのがほとんどでした。二人いれば儀式の分担がきちんとできます。前住職が動けなくなってからは、私一人で勤めることも結構ありました。そのときは喪主によそから坊さんを呼ぶようにするかどうか確認して、呼んで欲しいと言われれば呼びます。最近、娘・息子が手伝うようになっていますので、よそから呼ばなくても何とかなりそうです。
これは母の本葬の時の写真です。寺族の葬式ですので坊さんがいっぱいいます。普通の人の葬式の場合は、
前住職がまだ仕事ができた時は、二人で勤めるのがほとんどでした。二人いれば儀式の分担がきちんとできます。前住職が動けなくなってからは、私一人で勤めることも結構ありました。そのときは喪主によそから坊さんを呼ぶようにするかどうか確認して、呼んで欲しいと言われれば呼びます。最近、娘・息子が手伝うようになっていますので、よそから呼ばなくても何とかなりそうです。
次に本堂で行う葬式で一般の人の場合の写真を出します。これは新しくなった本堂ですね。
 |
 |
供花や供物はこのように廊下側に並べるようにして、本堂の祭壇の周りには置かないようにしています。この方の場合はお通夜から本堂で行いました。新しくなって、エアコンも入ったので宿泊も快適になったと思います。最近、寝具類も4、5人分は揃えました。
9.繰上法要・中陰
 母の場合に戻ります。葬式の後、すぐに納骨してその後繰上法要を行い、お斎も済ませ一連の流れが終りました。
母の場合に戻ります。葬式の後、すぐに納骨してその後繰上法要を行い、お斎も済ませ一連の流れが終りました。
その後は中陰壇を飾りますが、納骨は済んでいるので骨箱はありません。一般には四十九日過ぎてから納骨することが多いので中陰壇をお骨を飾る場所と考える人がいるかもしれませんが、中陰壇はお骨あるなしに関わらず設置します。そして四十九日までは花瓶に挿す植物は櫁だけです。
以上、葬式の流れを説明しました。つぎに色々気になる点をお話します。
・遺影を飾ることについて
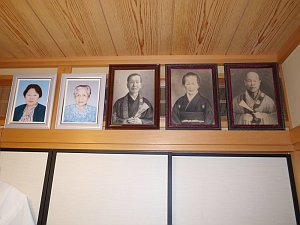 遺影(写真)については葬儀屋さんが始めたことではないかと言いました。やはり儀式には余計なもので、坊主の立場としてはずっと邪魔者扱いしていました。しかし、一応世間的な格好もつけておかなければならないか、と母の時も写真を飾っています。一般の人の葬式の時に写真は飾らなくてよいなどとは言ったことがありませんので、ご安心を(一同笑)。
遺影(写真)については葬儀屋さんが始めたことではないかと言いました。やはり儀式には余計なもので、坊主の立場としてはずっと邪魔者扱いしていました。しかし、一応世間的な格好もつけておかなければならないか、と母の時も写真を飾っています。一般の人の葬式の時に写真は飾らなくてよいなどとは言ったことがありませんので、ご安心を(一同笑)。
しかし、ある門徒さんがガンになって自分の葬式の相談に来られたことがありました。その話の中で「写真はどうしても飾らなければならないのですか」と聞かれました。遺影を飾るのが嫌いなのだそうです。私はああこういう人もいるのだと嬉しくなり、その必要は無いということを説明しました。そうしたらホッとしたようです。
と言いながら自分の母親の写真はしっかりある(一同笑)。そして葬式が済んだ後は物置にしまい込みました。その前に亡くなった者の遺影も同様で、この庫裡を新築してからは遺影は一切飾っていなかった。しかし最近、これらは家族の歴史だなと思うようになりました。せっかくあるのだから、これからの家族に伝える材料としてはいいものだ、と百八十度考えを変えて、このように仏間に飾ることにしました。
・引導を渡す
引導を渡すから「導師」というのです。儀式では導師が一番偉い。私も導師をします。では私は引導を渡しているかというと、渡していません(笑)。では引導を渡すとはどういう意味かというと、本来の意味は師匠が弟子を指導するということですが、葬式の場合でいえば「死者を極楽に送る」というものになるでしょう。導師はそういう超能力があるとされるわけです。ところが、私共の宗派の場合は超能力を認めません。すると、葬式が死者を極楽に送るための儀式でなければ何のためにやっているのかということになります。私共の宗派の場合は極楽に行くかどうかは亡くなった人本人が決めるべきこと、ととらえます。本人が阿弥陀仏の教えを聞いて本心から南無阿弥陀仏と称えればその時に極楽往生は決まる。本人と阿弥陀仏との直接の関係です。しかし、これは本人が生きているときの話です。本人が亡くなってからの魂(魂が有るのか無いのかという問題にはここでは入りません)に対しては、坊主の立場としても踏み込めません。
では真宗の坊主はなぜ引導を渡さない導師をするのか。それは、亡くなった人がもし極楽に行っていれば、その人への讃嘆――誉め称えるために行う。涅槃という最高の喜びを得た人を誉め称えましょう、と儀式を行う。しかし、これは何度も言うように建前の立場です。普通、そういう亡くなり方をする人はいないと言っていい。しかし、そういう人に対しても讃嘆の立場で行う。
しかし、他宗の場合は導師の力で送る、という立場が多い。私は一般の参列者として、浄土宗の葬式に出たことがあります。この時導師から「故人を極楽に送るために皆さん一緒に念仏を称えましょう」と言われてびっくりしたことがありました。浄土宗と真宗ではベースになる経典が一緒なのですが、極楽や念仏を全く違った意味でとらえている。私達が称える念仏の力で故人の魂を極楽に送ろうというのです。私はびっくりして(さらに失礼ながら笑い出しそうになって)一緒に念仏を称えることができませんでした。宗派の違いをつくづく感じさせられました。
・音楽を流す、ビデオやスライドを見せる
葬儀屋さんの会館などで、よくやるものですね。故人の好きだった音楽とか、スライドショーとかビデオを流す。儀式中にこういうことをすることはさすがに最近はないですが、昔は儀式中に音楽を流されたことがあった。この時は儀式中の音楽はやめてくれと苦情を言いました。葬儀屋さんも喪主や故人の気持ちを思って、できるだけその意向に沿うようにとやっているのでしょうが、前回の船からの散骨の話でもそうでしたが、どうも感情の流れに乗せて進めることがいいことだ、みたいな風潮がある。私はこれはちょっと困ったものだと思っています。寺に居て葬式を勤める者としては、このような感覚とは隔たりを感じます。全部否定するつもりは無いのですが、無反省にそこに走るのはどうなのだろうかと。
2014/07/31 公開