�z�[�� > �G���E�����E���� > �f��uhappy�v�ӏ܉�
�f��uhappy�@�����킹��T�����Ȃ��ցv�ӏ܉�
�Q�O�P�T�N�Q���Q�P���@�����̉�

�摜���N���b�N����Ɣz�����̃T�C�g�ɔ�т܂��B
����
2��9���ɁA���̈ē����Ɣz������������`���V��S��k�ɔ��������B�܂�������3�ӏ��Ƀ|�X�^�[��o�����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@
�@���̉f����挎�̓����̉�Řb��ɏo���������ł��B�l���K����������Ƃ��̓��e�����܂��܂Ȗʂ��疾�炩�ɂ��Ă���h�L�������^���[�ł��B�����ɂƂ��čK���Ƃ͉��Ȃ̂����l�������Ă���܂��B����͂܂������̐S�̂�����Ɛ[����������Ă��邱�Ƃł�����܂��B
�@���̉f��͒��w���ȏ�̐l�ł���A���Ă悩�����Ǝv���ł��傤�B�ǂ������C�y�ɁA���Ƒ��E���F�B�E���l�Ƃ��U�����킹�Ă����ł��������B
�����Ă���ƒm��ʊԂɗ܂��o�Ă��邱�Ƃ�����܂��̂Ńn���J�`�����Y��Ȃ��B�܂������\���Ȃ̂Ń��K�l���|������͂��Y��Ȃ��B
�@
�����@2015�N2��21���i�y�j���j
�@13:30�@��t�J�n
�@14:00�@��f�i76���j
�@15:20�@�x�e
�@15:30�@���k
�@16:00�@�I��
�����@�P�l500�~�@�i������t�ł��x�������������B�j
�\���@���Ȃ��������邽�߂P�X���܂łɎQ���l����d�b�ł��m�点���������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�f��̏�f�͏��߂ĂŁA�@�ނ͂����g���Ă���v���W�F�N�^�[�ƃX�N���[���A�m�[�gPC���g�p�����B�X�s�[�J�[�����Ŏ����ɐݒu���Ă���X�s�[�J�[�ƃA���v�ɂ͒��ڌq���Ȃ����Ƃ��킩�����B������25�N�O���炠��BOSE��AW-1�Ƃ������W�J�Z�i�Ƃ������A�X�s�[�J�[�ɂ��܂��ă��W�I�ƃJ�Z�b�g���t�������́j���剹�ʂ��o����̂ł�����m�[�gPC�Ɍq�����B
����
13:30�@��t�J�n
�@26���Q���B
 |
 |
14:00�@��f�i76���j
 |
 |
�f��̊T�v�B�o�ߎ����Ɖ摜�ɂ��_�`�B
�i�z�������������摜�̂ݎg���Ă��邽�߈ꕔ�摜�̂Ȃ��R�}������B�j
 1:35 |
 4:40 |
 6:15 |
| �C���h�E�R���J�^�̕n���X �}�m�[�W�E�V�� �n�����Ă��K�� |
�C���m�C��w �S���w���� �G�h�E�f�B�[�i�[���m �K���x�̒��� |
�J���t�H���j�A��w ���o�[�T�C�h�Z �S���w���� �\�j�A�E�����{�~�A�X�L�[���m �K���x��4�����₹�� |
 7:50 | 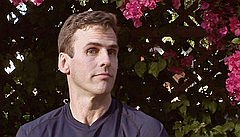 9:47 | 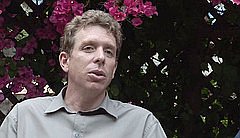 9:50 |
| �A�����J�E���C�W�A�i ���C�E�u�����`���[�h�E�V�j�A �厩�R�ɐg��u�� |
�x�C���\��ȑ�w �]��w���� P�E���[�h�E�����^�M���[���m �_�o�זE�Ԃ̃h�[�p�~���̘A�� |
�G�����[��w ���_��w���� �O���S���[�E�o�[���Y���m �h�[�p�~�������o��������� |
 11:40 |
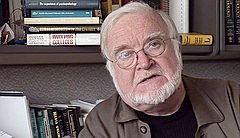 14:20 |
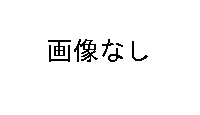 16:00 |
| �u���W�� �z�i�E�h�E�t�@�h�D�[ �g��߂܂���x�ɍ��g���� |
�N���A�����g��w�@�S���w���� �~�n�C�E�`�N�Z���g�~�n�C���m �t���[�B�s�ׂ��̂��̂����@ |
�W���}�� �~�[�̌y�� |
 16:20 |
 17:00 |
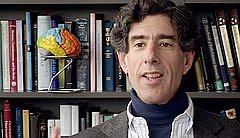 23:20 |
| �_�j�G���E�M���o�[�g���m ��т��߂��݂��Z���Ԃŏ����� |
�����b�T�E���[�f�B�[ �������o�Ă̕��� |
�E�B�X�R���V����w �}�f�B�\���Z �S���w���_��w���� ���`���[�h�E�f�r�b�h�\�����m �t���͈����Ƃ͌�����Ȃ� |
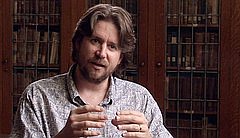 24:20 |
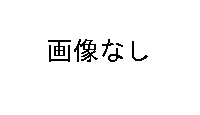 25:50 |
 32:10 |
| �m�b�N�X��w �S���w���� ���C���E�L���T�[���m 50�N��2�{�������ɂȂ������K���x��50�N�O�ƕς��Ȃ� |
�u�����`���[�h�� ���R�̌b�݁B�����̐H���͈�K���������ĂȂ� |
���{ ���씎�q �v�̉ߘJ���B���ʂ����Ƃ͐l�Ԃ̂�Ƃ�����B |
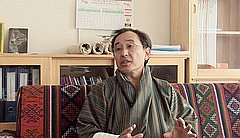 36:00 |
 37:00 |
 39:20 |
| �u�[�^�� ���ʐM�� �_�V���[�E�L�����C�E�h���W ���������Y�ł͂Ȃ��������K���� |
�V�o�ϊw���c �K���Z���^�[��\ �j�b�N�E�}�[�N�X �ړI�͐l�X�ɒ����K���Ȑl���𑗂��Ă��炤���� |
�f���}�[�N �A���E�x�b�N�X�K�[�h �R�E�n�E�W���O�i�����Ƒ��̋��������j |
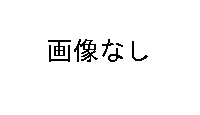 44:50 |
 46:30 |
 53:20 |
| ����r�˂���@���̗� �ɓx�̌�����`�҂͎����B�ȊO�͒n���ɍs���ƐM���Ă��� |
���� �����E�V 106�� �K���x�͒������ɂ��q���� |
�R���f�B�A��/����� �}�C�P���E�v���`���[�h ���w�̎��ƁB���҂ƌq���邱�ƂŊ�т͐���� |
 59:00 |
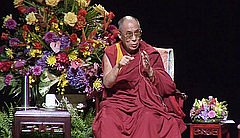 1:02:00 |
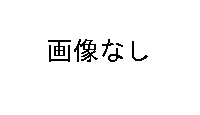 1:04:00 |
| �i�~�r�A�E�J���n�� �N���_�E�{�[ ���㕶���ȑO�̍K���B�����͂ƂĂ���� |
�_���C�E���} ��Ǝq�̈���B�@���ł��Ȃ����`�ł��Ȃ��B |
���Ȋw�҂Ń`�x�b�g�m �}�`�E�E���J�[�� �����D�������ґz�B�R�T�܂𗽂��B |
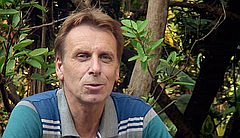 1:07:00 |
||
| �C���h�E�R���J�^ ����҂l�X�̉ƁE�{�����e�B�A �A���f�B�[�E�E�B�}�[ �x��h�_�ĉƑ�����ĂĂ���ŏI�肩?��ɍl���Ă����B |
15:20�@�x�e
�x�e���Ɏ��̂悤�ȓ��e�̃A���P�[�g�p����z��A�I�����ɉ�������B
�@
happy�������ɂȂ��ẴA���P�[�g�@
�P�@�����z�����������������B
�Q�@��������̂悤�Ȋ���]�܂�܂����B
�i�P�j�]��
�i�Q�j�]�܂Ȃ�
���Ă͂܂�ق��Ɂ������Ă��������B
�A���P�[�g��26����25������o�B
���Ɋւ��ẮA24�����]�ނɁ���t�����B1�����Ȃ��B�]�܂Ȃ���0�B
�@ �A���P�[�g���z����
�@
| ��ϑf���炵���B���肪�Ƃ��������܂����B | ���{���O�����݂ȓ����ł悢�l��邢�l�̍����傫���B |
| ����҂l�̉Ƃ�����Ƃ͋����܂����B | �D���Ȏ����o���Ă��鍡���K���Ɗ����܂��B�o�ύŗD��̍��̓��{�ɁH |
| �K���͎����������K���ł͂����Ȃ��B�݂Ȃ���Ƌ��ɕ��������Ă�����Ǝv���܂��B | ��Ԃނ���������Ԃ���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂����B���E�̂��낢��ȍK������Ɗ����܂����B |
| �K���͎������g�ō����̂ł��邱�ƁB�����Ď������K���Ɗ����鎖���̂��̂��K�Ȃ̂ł���B�����ȏ����Ȃ��Ƃł�����Ȃ�Ɋ�т��������鎖���K���Ȃ̂����ˁB | ���߂čK���Ƃ͂ǂ��������̂��������܂����B�K���͕�����ł͂Ȃ����������Ă����鎖�ɂ�蓾������̂��Ȃ��Ǝv���܂����B�l�����l�����ő�ώQ�l�ɂȂ�܂����B |
| �K���͎����̐S�̂�����Ŋ�������̂��Ǝv���܂����B�h��͐l�ׂ̈Ȃ炸�h�l���K���ɂ���Ύ������K���ɂȂ��B�ƂĂ����ɂȂ�܂����B�K���ɂȂ邽�߂ɂ͓w�͂��K�v�B | �������R�Ɛ����Ă��鎩���ɋC�Â��܂����B���̋@��Ɏ����Ȃ�ɍK���ɂ��Ď��͂����܂킵�l�������Ǝv�����B |
| �K���Ƃ͋������A�H�ו��L�x�A�܂��͗��s�����ł��邱�Ƃ��������������Ă��ꂪ�K�����Ȃ��Ǝv���Ă�����A���E�e���̐l�Ƃ̌𗬁A�F���ǂ����ĕ�炵�Ă����鎖��Happy�Ɗ����܂����B | �K���͒n�ʂ▼�_�Ƃ������łȂ����X�Ƒ��A�F�B�A����̕��Ƃӂꂠ�������ȏ������������Ȃ����J�̂����������K��������������Ƃ������Ƃ��ӊO�Ɏv���܂����B |
| ���E�ܑ嗤�̍K���ɐ������Ă���l�X�A���������K���ɑ����Ă���Ƒ��������B���݂̓��{�����Ő������Ă���q����Ƒ��A�e�ށA�����A�s���Ŏ����̐����ɍ����o���邾�����݂����������A���͂��Ă������Ȃ�K���Ȑ����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B | ���������肪�Ȃ��̂ɏ���茩�グ�Ă��錻�݂̎����ɏ������₯�������B���{�̐e�q����ɗ���ĕ�炳�Ȃ�������Ȃ�������A�Љ�g�D�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����̂��H �l�̍K�s�K�͂��̐l�łȂ���킩��Ȃ����̂��B |
| �u�K���v�������ȁ@���B�̂܂��ɂ��܂�ɂ����Ȃ��Ȃ����悤�ȋC�����܂��B���a�̎���ɂ������ǂ������c�������ł��B����ǂ�ł͂Ȃ��A�ӂݐH�ɂ��đO�ɐi�݂����B�����ɗ^����ꂽ���̂��K�Ƃ��Ď�����ꂽ��B���肪�Ƃ��������܂����B�����̂��������Y��܂���B | �������傤�ǎ��̎�l�̌������ł����B�������C�ŋ��邱�Ƃ���l�����S���ċx��ł�����Ǝ����Ɍ����������Đ������Ă��܂��B�������炵���K���Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ̕��������Ă��炢�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B |
| �l�l���ꂼ��̂��낢��ȍK��������A�g�߂ȏ��ɂ�����̂Ȃ̂��Ɖ��߂Ċ����܂����B�C�����̎������ōK������������B��ϕ��ɂȂ�܂����B�l�ƂȂ����Đ����Ă���������Ȃ̂��Ǝv���܂����B | �K���̉��l�ςɂ��ĉ��߂ċC�t�����Ē����܂����B���ʁA�����Ɍb�܂�Ă�����{�ł͖{���̍K���������邱�Ƃ�����悤�ɂ��v���܂��B�����Ȃ��ƂɊ��ӂ������ł���悤�����������ł��B |
| �K���Ƃ͂ނ��������B�����������̍D���Ȃ��Ƃ����Ă��鎞�͎��Ԃ��C�ɂ������܂ł��ł��A�H������炢�����Ă��C�ɂ��Ȃ��B�����������钇�ԂƎ����Ȃ��Ƃ������Ȃǂ͒B����������K���Ɗ�����B | �K���Ƃ͊e���Ⴄ�Ǝv���̂ł����A�����Ɏ������������邩�A���������ɂƂ��Ė����ł��邩�Ȃ������A�Ƒ��A�F�l�n��Љ�̐l�B�Ƃ̌𗬂��ǂ�����ׂ����A���̎������K�������l���������܂����B |
| �����A�܁X�̉f��ƕ����Ă����̂ŁA�o�Ȃ��邩�ǂ����������̂ł����A���̓x�A�ӏ܂����Ă��������悩�����ł��B���肪�Ƃ��������܂��B��X�v���Ă������ƁA�����Ă������Ƃ��A��͂�A�Ƃ����v���Ŋm�F������ꂽ�C�����ł��B�����̍l���Ă��邱�Ƃɏ������M�������Ȃ���O�ɐi�݂����Ǝv���܂��B �i�ނ����������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����̏o���邱�Ƃł悢�̂��Ǝv���܂��B�j | ���ꂼ��l�ɂ���āu�K���v�̎ړx���Ⴄ�Ƃ������ɋC�Â�����ꂽ�B�i���܂ňȏ�Ɂj ���l���猩��K���Ȑl���Ǝv���Ă��{�l�͋C�Â��Ă��Ȃ��l�������ς�����B�ǂ��܂ł��u�K���v�ł���Ƃ������܂肪�Ȃ�����ł��낤�B���͕��ʂɕ�炵�Ă�����̂ł���u�K���v�Ǝv��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���{�ɐ��܂�Ė{���ɂ悩�����v���Ă���B�����ċC�����𖾂邭�������Ă�����Ɗ���Ă���B |
15:30�@���k
�Z�E�@�R�O���قǍ��k�̎��ԂƂ��܂��B������f�����͓̂��{�ꐁ���ւ��łł����B����͉f��̔z�����ɐ\�����ނƑ����Ă�����̂ł��B�����ď�f���I������Ԃ��Ȃ�������Ȃ��B�����ł�DVD�������Ă���̂ł����A���蕨�̕��͐����ւ��łł͂Ȃ������łł��B�ł�����F���������Ǝv�����Ƃ��͂����𒍈ӂ��Ă��������B
�@���Ď��͂��̉f����ŏ��ɃC���^�[�l�b�g�̃f���N��TV�ŊςāA���ꂩ��DVD���܂����B������DVD�͊ςĂ��炸�A���̌㍡��̊ӏ܉���v�悵�܂����B�����č����A�F����ƈꏏ�ɂ�����x�ς��̂ŁA2��ς����ƂɂȂ�܂��B����2��ڂ��ςȂ��猋�\�Y��Ă���Ǝv���܂����B�ŏ��Ɋς��̂�1���n�߂ł����̂ŁA�ꌎ�����炢�Ő����Y��Ă���B���ς�������ŏI���Ă��܂��Ǝ�肱�ڂ������Ȃ肠��B�܂葊�����e�̔Z���f�悾�Ǝv���܂��B�������Պς������ł͏\���łȂ��A���Ղ��ςȂ��Ƃ��������Ȃ��B
�@���̖Y��Ă������Ƃ̈���A�@���̈��������̖�肪�o�Ă��܂����B���_�����k���C�X�������k��r�˂���Ƃ��A���邢�̓C�X�������k���L���X�g���k���E���ƌ����Ƃ��A�q���Y�[���k���C�X�������k���E�����Ƃ��A����������ʁi44���̂�����j�����������o�Ă��܂������������������Y��Ă��܂����B�������Ȋw�҂������Ă��܂����ˁA���̐l�B�͕��ʂ̐l���s�K���ƁB
�@�����Ď������̉f����ŏ��Ɋς��̂�1���̎n�߂ŁA�C�X�������ɂ����{�l��a�莖���͂܂��N���Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪2���̎n�߂Ɏ������N���āA���̌�̍���������x���̉f����ς邱�ƂɂȂ�܂����B�����Ă��̉f�悪�\�������ɔޓ��̐U�������������ĂĂ���B
�@���B�͂��̉f��Ō����Ă���悤�ɍK�����������܂��B����������̎����̂悤�ɐ��܂���������炩����Ă��܂��ƁA�K���̓y��Ƃ������悤�Ȃ��̂�����������������悤�ȋC�����ɂȂ��Ă��܂��B���{�Ƀe�����X�g�������Ă���̂łȂ����Ƃ��A���{���{�͂Ȃ�ĂԂ��܂ȑΉ������Ă��ꂽ�Ƃ��A���������s����s���ɏ���Ă��܂��B��������Ǝ������K�����Ǝv���Ă������Ƃ��A����������̂��A�Ƃ������^���������B
�@�ł�����͂���ς�Ⴄ�ȂƁA���̉f���������x�ςĎv���܂����B��͂�A���̂悤�Ȏ������N���A���͂ǂ������{�I�ɊԈ���Ă���B���ꂪ���ƋK�͂ł̕����ɂȂ��Ă��܂��ăA�����J����{��������悤�ȂǂƂ����B�������邱�Ǝ��̂������Șb�ŁA���͂̂Ԃ��荇���ł͉v�X���Ԃ��������Ă��������ł��傤�B�����������̒��̕��͋C�ɂ���ƁA�����̂����₩�ȍK���̊�Ղ����͂ɂȂ�悤�Ȋ���������B����������C�ɂȂ肪���ł������̉f����ς�ƁA��͂�Ⴄ�ȁA�Ƃ�����x��������{�Ƃ��ׂ��Ƃ���ɋA��܂��ˁB
�@�܂�l�̍K�������������肵�Ȃ������萢�E�͂������肵�Ȃ��B���Ȃ킿�A���̂悤�ȋC�������݂��s�ׂ����������[�����čK���ɂȂ�Ƃ������Ƃ��d�v���Ƃ�����x�v���Ԃ��B
�@�f��̍\���͕����̘b����o�ė��܂������ɕ����ɊW����Ƃ������̂ł��Ȃ��B�������A�f��Ō����Ă��邱�Ƃ͂��o�Ō����Ă��邱�ƂƓ����Ǝv���܂��B��y�^�@�Ƃ������@�Ƃ��̏@�h�̈Ⴂ�ɂ������ƑΗ����N����B���������L���X�g���k��C�X�������k�̊ԂŋN���B�����͂���K�����̖����@���҂ł��B�����������x���ꂼ��̏@���̖{���̗���ɖ߂��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B�^�@�̌������ł͈���ɕ��͐��E���̂ǂ�ȂƂ���ɂł������A����Ȃ��Ƃ���͂Ȃ��A�ƌ����̂ł����A�ł͂ǂ��Ɍ���邩�Ƃ����Ɛl�̐S�̒��Ɍ����B���ꂪ�����Ō����K�����ł��B�`�������͂�����o��Ƃ��M�S�Ƃ������t�ŕ\�킵�Ă��܂������A���̉f��͌����ŕ\�킵�Ȋw�I�Ȍ����������Č������Ǝv���܂��B2��ڂɊς����̊��z�ł����B�F����̊��z�₲�ӌ������肢���܂��B
������Y�@�F�X�ȏ@���������ē��{�̏ꍇ���ƕ����ł����A�_�����̂��炠�����B���{�I�ɂ͐l�Ԃ̍K������ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B�_���ɂ��Ă������ɂ��Ă��B�S�̎��͎����̍K����������Ƃ���ɂ���B������O���@���͐l�̓��ɊO���B�K���͐l�ɂ���ĈႤ�Ǝv���̂ł����A������l�ł͂Ȃ��Ƒ���n��̐l��F�l�ƒ��ǂ����邱�Ƃ��K���ɒʂ���̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B���������Ƃ��Ƒ������Ƃ������l�������ł���������x���̂ւ���l���Ă݂����Ǝv���܂��B
�Z�E�@���肪�Ƃ��������܂��B��������ɓI�m�Ɍ����Ē����܂������A�݂Ȃ���������悤�Ȋ��z�Ǝv���܂��B
�g�c���q�@���̂��b�Əd�����邩������܂��A�K�����������Ė������߂����Ƃ��厖�ł��ˁB���̍K���͎�������i��ō���Ă������̂ł���B�������K���Ɗ����邱�Ƃ��̂��̂��K���ȂƁB�����������Ȃ���A�͂�����K�������Ɍ����Ă��K���ł͂Ȃ��B�����Ȃ��Ƃł������Ɋ�т������邱�Ƃ��ł���K���łȂ��̂��ȁB�����������͎̂����Ō����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Z�E�@�����Ŏ���Ȃ̂ł����A�����������̂������悤�Ƃ��Č�����ꂸ�ɐl�͔Y�ނƎv���̂ł����E�E�E
�g�c�@�Ⴆ�ΐA�ؔ����P�O�O�~�Ŕ����܂��ˁB�Q�ɂȂ�Ԃ��炢���Ƃ��A�����炢���̂��Ƒf�ʂ肷��悤�ȋC�����ł͌������Ȃ��ł��ˁB�킟�炢���Ɗ�ԋC�������Ȃ��ƁB
�Z�E�@�f��̒��ʼnȊw�҂��u�Ⴆ�W���M���O�̃R�[�X��ς��Ă݂�v�ƌ����Ă��܂��������������Ƃ�����w���Ă���Ǝv���B���t���������Ɖ������ĂA�Ƃ�������ۂɂȂ�܂����B�f��ł͐F�X�Ȗʂ���w�E���Ă��܂����A��X�̖����̐����ł͓�����O�����Ă����ɋC�Â��̂�����B
�������@�����������͍̂��������Ă��Ȃ��Ă�����͍K�s�K�ł͂Ȃ��B�܂��f��̒��̎��̂̂悤�ɕs�K�̒��ɂ����Ă��A���̓s�x�i��ł����Ζ��������o�Ă���B�n�ʂ������Ă��Ȃ��Ă��K�s�K�ɊW���Ȃ��B�K���Ƃ����͎̂����ō���Ă������̂��Ɗ������킯�ł��B���̑��Ɍ������Ƃ��Ȃ��B�i�ꓯ�j
���˕��@���ꂼ��̍��ɂ���Đ����̈Ⴂ�����邪�A�Ƒ��̘a�Ƃ��v�����������Ƃ��K���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
�Z�E�@���̃}�X�R�~��j���[�X�Ȃǂ�����ƁA���̉f��̂悤�Ȍ������Ƃ����t�̎g���������܂���ˁB���ƍ����Ԃ������A��������������ɂ��Ă��A�����ɓ����l�̂��Ƃł͂Ȃ������鐧�x��b��ɂ���B���邢�͍��̃����c����ɂ�����B��������Ƃ��������A�����Ă���{�l�������ɂ��Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��B�{�l�̋C�������`����Ă��Ȃ��B���������Ƃ��낪��X�̎Љ�̖��̂悤�ȋC�����܂��B���̉f��̂悤�Ȍ������}�X�R�~�ɂ��������L����A�������t���Ă��Ă�����������Ă���Ǝv���̂ł����B
�����@�f��̒��ŃC�X�������̂悤�Ȗ�肪�o�Ă������A������K���ɓ���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă����悤�Ɍ����邪�E�E�E
�Z�E�@�ً��k��r�˂���Ƃ��A�E���Ƃ������Ă��镔���ł����B����͍K���ɂ͓���Ȃ��Ɖf��ł͐������Ă���E�E�E
�����@�������Ƃ��Ă��A�{�l�B�ɂƂ��Ă͂��ꂪ�����ɂȂ�B���������l���������ł��Ȃ��B
�Z�E�@�܂肻�������l���ɋÂ�ł܂��Ă���l�B�ł��ˁB���̍l���ɂ����݂��Ď����͍K�����Ǝv������ł���Ƃ������Ƃł��傤�B���̑���l���E���킯���B�E���Ȃ��l���o�Ă������B
�@�����ɂ͏\�P���Ƃ������t������܂��B�F����̒��ɂ͑����@�̒h�Ƃ�������������邩������܂��A�����@�ł͉��͂Ȃ��݂̂��錾�t���Ǝv���܂��B�t�ɐ^�@�͉��Ƃ������t���قƂ�ǎg��Ȃ��B���������͕������ʂ̌��t�ł��B���Ƃ͂���Ă͂����Ȃ����ƁA�Ƃ����Ӗ��ł��B�����@�̑����ɏo��ƁA�S���Ȃ����l�ɉ���������Ƃ����V��������B�܂������̋����̂��Ƃ����@�ƌ����B�܂����Ă͂����Ȃ����Ƃ����Ȃ�����Ƃ����̂��ł̋������Ƃ����킯�ł��B��X�̏@�h�͂������������������Ȃ��̂������{�͓����ł��B���Ă��̉����\����܂��B���̈�ɕs�E�����Ƃ������̂�����B�������̂��E���Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������ł��B
�@���̉��߂ɂ͓����肪����܂��āA�ǂ�Ȑ������̂����E���Ă͂����Ȃ��ƂƂ炦��ƁA�����͐H�����Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��̂����A�A�����������E���Ă͂����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA������������Ȃ��Ƃ͎��Ȃ��Ƃ����l���ɂȂ�܂��B�������s�E�����̖{���̈Ӗ��́A�����������邽�߂ɂ͑��̐������̂��E����������Ȃ��Ƃ������Ƃ�F�߂������ŁA�s�v�ȎE���͂���ȁA�l���E���ȂƂ������Ƃł��B�����ėv�_�͐l���E���ȂƂ������Ƃł��B�l���E������n���ɗ����܂��B����͕����̂ǂ̏@�h�ł�������O�̂��Ƃł��B�����痧�h�Ȃ��Ƃ������Ă��l���E������S�R�_���ł��B�C�X�������̎��l�͂��������Ă���B
�����@�l���E�����@�͎���ɂ���ĈႤ�Ǝv���B�Ⴆ�ΐ퍑����ɍ��V���̉f��́u���l�̎��v�̂悤�ȏŁA�l���E���Ȃ���Ύ����B���������Ȃ��ƂȂ�����A�E����������Ȃ��B����̃C�X���������߂���ł��A�����͂�肽���Ȃ��̂ɎE����������Ȃ��A���邢�͋�������ĎE���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l������Ǝv���B���������l�B�͐l���E�����Ƃɂ���Ď����͓V���ɍs����Ƃ��������@���I�ȍl�������荞�܂�Ă���B������n��Ƃ�����ɂ���Ċ��������Ⴄ�Ǝv���B
�Z�E�@���������ƂŒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B�����e���ȂǂŎ������Đl���E���Ď��������ʂ��Ƃƈ����ւ��ɓV���ɍs����A�Ƃ܂������܂߂��Ď��s����Ǝv���̂ł����A���̍l���͊ԈႢ�ł��B�����炭�{���̃C�X�������͂���ȍl�����͂��Ȃ��Ǝv���܂��B�܂荡�̌����ɐ����Ă���䂪�g���E���āA�ʂ̂����Ƃ������E�ɍs���Ƃ����l���́A�@���̂ӂ�������R���ł��B�����̏ꍇ�A�o���Ƃ������Ƃ͐���ς���Ċo���Ƃ������Ƃł͂���܂���B���A�o��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ċo����琶�܂�ς������܂ŐӔC�������Ă��܂��B����������̂ł����A���Ԃ�L���X�g���ł������悤�ȍl�������Ǝv���B�_�Ƃ̊W�͎���ł���ł���̂łȂ��A���A�_�Ƃ̊W���ǂ��������̂����͂�����Ɖ���Ƃ����̂��j�S���낤�Ǝv���B�����āA���o���Ƃ��A�_�Ƃ̊W������Ƃ��������Ƃ́A���̉f��Ō����Ă���K����Ƃ������Ƃƒʂ��Ă���Ǝv���B
�����@�C�X�������ɍs���悤�Ȏ�҂́A�����̍��Ő������ꂵ������ɒǂ����܂ꂢ��l�������B�����炻�ꂼ��̍�������������҂̋�����ǂ����Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�Z�E�@���̂Ƃ���ł��ˁB�����āA���̒n��͂��������ɂȂ�܂ł��Ɖ��\�N�A���S�N�Ƃ�����悤�ȓD���ɓ����Ă��܂����Ǝv���܂��B
���{���q�@���͍����F�B��4�l���A�ꂵ���̂ł����A���̂���3�l�͒����̃{�����e�B�A�Ŗ�����N���B�̂������݉�̂����b�����Ă���B���̂��߂Ɏ��O�ɉ��W�܂��ď��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�߂�ǂ������ȁA���\�ɂȂ������玩�������b���Ă��炤�ق��ɓ��낤���ȂȂǂƍl���Ă�����������̂�����ǁA���k�����B�̒��ɓ����Ęb���Ă���Ɓu���˂��A�����ɗ���̂��w�܂萔���đ҂��Ă���́v�ƌ����Ă����B�u�{���Ɋy�����́B�Ƃł͉ł����邯�Ǔ����Ă��āA�����͂ЂƂ�ڂ���������v
�@���̐l�͂����ƌ��C�ȂƂ��͂��ٖD���D���ŐF�X�Ȃ��̂�D���č���Ă��������͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�F�B���݂�ȕ����Ȃ��Ȃ��ė���Ȃ��Ȃ����B�����Ă������݉���w�܂萔���Ă���Ƃ������t�����Ƃ��A�����{���Ɋ��ł���Ă���l������ȂƎv�����B�����炨���b���鎄�B���撣�낤���A�ƁB�݂�Ȃ��ꂼ��Z�����̂�����ǁB���̊Ԉ�ɂ���̐u�̃T������ɂ����ז����܂����B�����������Ƃ��K���Ȃ̂��ȂƎv���܂��B
�g�c�@�K���Ƃ������Ƃ��炿����ƊO��邩������܂��A�C���h�̃R���J�^�̏�ʂ�����܂����B���̕n�����̒��ł��K��������Ƃ������Ƃ�\�킵�Ă���͉̂���܂��B�ł����͂�������č��̓��{�̗ǂ����Ĕ������܂����B���{�͐�ォ��F�X����܂������A���̂悤�Ȑ����͑S���ǂ�����������Ă��܂����B�����̃��x�����S���ŏオ�����B�����������{�̂��炵���������܂����B
�Z�E�@���̂��b�ɕt��������ƁA�̔��pDVD�ɂ͓��T�f���Ƃ������̂��t���Ă��܂��B����҂͊ē��A�����J�l�ł����A������l���{�l�����܂��B���ۂ͂��̓�l�ō���Ă���悤�ł��B���T�f���ɂ��̐l�������Ă���Ƃ��낪����܂��B���̒��ł��̉f����ς����{�l�̊��z���u������Ɠ��{�Ɍ���������̂ł͂Ȃ����v�ƌ���ꂽ�A�ƌ���Ă��܂��B�܂���{�̂����ʂ�����̂ɂ�����o���Ȃ��Ł\�\����͏o���܂������\�\�ߘJ���̖����o�����B�Ƃ����ӌ��������������ł��B
�g�c�@�C���h�̕n���̒��ł̍K���̗Ⴊ�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł���B�ł����{�͂������������������Ȃ��Љ��z�����Ƃ��ł����B
�Z�E�@���������b�܂ꂽ�ɉ�X�͂���Ƃ������Ƃ����ӂ��ׂ��Ȃ̂ł��ˁB
�g�c�@���ӂ��Đ�������B���̕ӂɂ��K���������Ă����B��������ƂȂ��ǂ��B